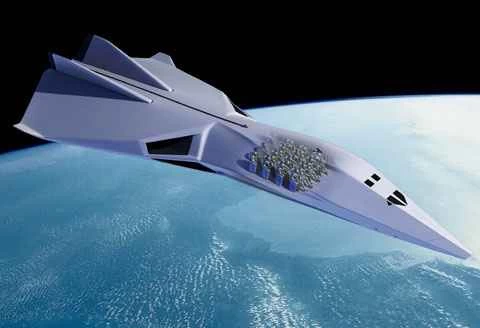
カリフォルニア大学バークレー校バレー生命科学ビルの地下室で、生物学者マイケル・ディキンソンはコンクリートブロックの廊下を歩き、無名の鉄の扉へと向かう。その向こうには、窓のない小さな部屋があり、そこには高速ビデオカメラやレーザー、そしてクモの巣のように密集したコンピューターケーブルがぎっしりと詰まっている。部屋の中央には、自動販売機が置けるほどの大きなガラスの水槽がある。これがロボフライだ。
タンクは空っぽに見える。機械のアームからぶら下がっている、昆虫の羽根のような形をしたプラスチック片だけだ。しかし、ディキンソンがフィルターをオンにすると、タンクからクリーミーな泡の霧が噴き出す。タンクにはなんと2トンもの鉱油が詰まっているのだ。ディキンソンがキーボードを叩くと、羽根がゆっくりと油の中を動き始める。羽根が前後に揺れ、無秩序な雲だった泡が、スローモーションの渦巻きと降り注ぐダイヤモンドのカーテンへと変化していく。
ディキンソンはロボフライの前に立ち、次々と渦が巻き起こる様子を注意深く観察している。本物のショウジョウバエ――間違いなく他の実験から逃げ出したもの――が漂いながら、毎秒200回羽ばたき、目に見えない小さな渦を自ら巻き起こしている。しかし、ディキンソンはそれを無視する。ロボフライは、ドイツで最初のプロトタイプを製作して以来、10年以上も彼の執着の対象だった。当時、タンクには砂糖シロップを使っていた。「研究室のいたるところに砂糖が撒き散らされていました」とディキンソンは回想する。「メイドたちがストライキを起こしました。指導教官があのベタベタしたアメリカ人を何とかしてくれるまで、研究室の掃除を拒否したのです」
ディキンソンの科学へのアプローチを端的に表すなら、「粘り強さ」という言葉がぴったりだろう。彼は一度問題に取り憑かれると、解決するまで決して手放さない。キャリアのほぼ全期間を通して、彼は一見単純な疑問にとらわれてきた。「ハエはどのように飛ぶのか?」
エンジニアたちは数十年前に海を横断する飛行機の作り方を解明したが、昆虫の空気力学は未だ彼らを困惑させている。飛行機が揚力を生み出す仕組みは、単純な概念で説明できる。翼の上を流れる空気の圧力は翼の下の空気の圧力よりも小さく、その不均衡が翼を浮かせているのだ。しかし、昆虫は脳と呼べるものはほとんどないにもかかわらず、飛行機の能力をはるかに超える複雑な運動を行う。戦闘機よりも素早く旋回し、天井に逆さまに着地する。「昆虫は完璧に横向きに移動でき、前後に移動でき、その場で回転することもできる」とディキンソンは言う。「実験をするたびに、ゴマ粒ほどの小さな神経系が一体どうやってこんなことをするのか不思議に思うんだ」
その疑問から、彼はロボフライ(ショウジョウバエの100倍の大きさで1,000倍遅い)だけでなく、昆虫の飛行の秘密を解明するために設計された、ロボフライの花嫁、フライオラマ、ロックンロールフライアリーナなど、奇妙で素晴らしいマシンのシリーズを作り始めた。電子メールのハンドル名が「flyman」のディキンソン氏がこれらのデバイスから集めた答えは、将来、エンジニアたちが米粒大の自動操縦機を作り、他の惑星を探索したり、燃えている建物に飛び込んで犠牲者を捜したり、文字通り壁のハエのように敵軍をスパイしたりするのを可能にするかもしれない。「彼は生物学者の外見の下に優れたエンジニアの素質を持っている」と、ロボット飛行デバイスの構築でディキンソン氏と共同作業してきたバークレーの電気技師、ロナルド・フィアリング氏は言う。
昨年、ディキンソンの研究が評価され、彼はマッカーサー・フェローシップ(天才フェローシップ)を受賞した。これは5年間で50万ドルの助成金で、条件は付かない。マッカーサー・フェローは、卓越した創造性と、将来の重要な進歩を約束する実績に基づいて選出される。ディキンソンは、受賞を知ったフェローの一人だった。彼は婚約者とハワイのカウアイ島の森の奥18マイル(約30キロ)をバックパッキング旅行していた。街に戻って留守番電話を確認すると、研究室に電話するようにという慌ただしいメッセージが残っていた。しかし、折り返し電話する前に、雨で携帯電話が切れてしまった。グアバの木に群がるミバエを見に行った州立森林公園で、ようやく公衆電話を見つけた。
ディキンソンは小柄な39歳で、眼鏡をかけ、よくハイキングに出かけ、山男と間違われるほど濃いあごひげを生やしている。彼がハエと出会ったのは1980年代半ば、ワシントン大学で神経生物学の博士号を取得していたときだった。ショウジョウバエはこの分野のモルモットだ。人間の脳には1000億個のニューロンがあるのに対し、ショウジョウバエには約50万個のニューロンしかないからだ。ハエはニューロンのほとんどを使って感覚情報を収集する。目で光、匂いに敏感な毛で匂いを感知する、羽の裏側にあるこん棒のような形をしたジャイロスコープでバランスを取るなどだ。これらの信号は神経系に送られ、神経系は羽に命令を送る。羽ばたきの間隔は数千分の1秒しかないため、命令は単純でありながら極めて正確でなければならない。
大学院生だったディキンソンは、ハエの羽に取り付けられた天然のひずみゲージを研究していました。このゲージは、羽がどれだけ曲がっているかを感知するのに役立ちます。しかし、研究を進めるうちに、ある疑問が彼を悩ませ始めました。「ハエの羽が受ける力を理解していなければ、羽に取り付けられたセンサーの用途を理解できるだろうか?」と彼は疑問に思いました。
科学者たちは何十年もの間、風洞で昆虫の羽の模型を試験することで、まさにそれを実現しようと試みてきました。しかし1984年、ケンブリッジ大学の生物学者チャールズ・エリントンは、それまでに蓄積された測定値を検証し、数値が合わないことを発見しました。昆虫が実際に生み出す揚力の半分さえも説明できた人はいなかったのです。それ以来、研究者たちは昆虫が目に見えない形で飛行に揚力を加えている方法を数多く提案してきました。しかし、これらの理論を評価することは不可能でした。考慮すべき変数が多すぎるからです。「地球上のどんなコンピューターも、力の大きさを説明できません」とディキンソンは言います。彼は別のアプローチを取ることにしました。「とにかく測定してみましょう」
ディキンソンは、生きている昆虫が飛行する際に働く力を計測することはできないと分かっていました。たとえ人工の最小のセンサーでさえ、ハエの羽には取り付けられないからです。そこで彼は、代わりに機械仕掛けのハエを使うことにしました。難しいのは、ハエと同じ力をハエに感じさせることです。昆虫の周りの空気は、大型動物の周りの空気とは全く異なる挙動を示します。人間にとっては繊細で滑りやすいものですが、ショウジョウバエのスケールでは、空気は濃くて粘り気があります。
ディキンソン氏は、ドイツのマックス・プランク生物サイバネティクス研究所のカール・グッツ氏と共同で、最初のロボット翼を製作しました。幅5cmの翼を砂糖シロップの中で羽ばたかせると、はるかに小さなショウジョウバエの翼が空中で受けるのと同じ力がかかることを発見しました。ディキンソン氏とグッツ氏は翼を製作し、前後に羽ばたかせるためのシンプルなコンピューター制御モーターを設計しました。センサーを搭載した翼が砂糖シロップの中で羽ばたきながら、タンクにアルミの削りくずを注ぎ込みました。そして、渦巻く削りくずの映像を撮影し、センサーが記録した力と比較しました。
ディキンソンは、ハエが揚力を発生させるためにいくつかのトリックを使っていることを発見しました。そのトリックの一つは、翼を急角度に保つことです。翼の上を滑らかに滑空するのではなく、上空の空気流は翼の前縁に沿って渦を巻きます。この渦は翼上の気圧を下げ、追加の揚力を生み出します。
パイロットなら誰でも、翼を急角度に傾けるのは危険な戦略だと言うでしょう。飛行機が急上昇すればするほど、翼の上を移動する気流が翼の縁に付着したままでいるのが難しくなります。気流が完全に離れると、飛行機は揚力を失って失速します。しかし、ハエには飛行機にはない利点があります。翼を一定の位置に保持する必要がないのです。ハエは翼を非常に素早く前後に羽ばたくので、翼がストロークを終えるまでに翼の前縁の渦が分離する時間がありません。各ストロークの終わりに、ハエは翼を回転させて逆方向に羽ばたかせることができます。これにより新しい渦が生成され、古い渦は無害に滑り落ち、失速を引き起こすこともありません。
その後、翼幅25インチのロボフライを使った実験で、ハエがストロークの合間に羽を回転させることによって生じるもう一つの揚力源が明らかになった。回転する物体(例えば、バックスピンで打たれたテニスボール)は、上面の空気を引っ張り、物体上部の気圧を下げる。一方、下面の空気は反対方向に押し出され、気圧が上昇する。この回転力は、ハエが羽を羽ばたく際にも発生し、昆虫全体の揚力の最大3分の1を担うことができる。
ハエは自身の航跡から揚力を生み出すこともできる。ハエが翼を往復させるたびに渦を放出すると、渦は回転を続けながらゆっくりと遠ざかっていく。ディキンソン氏は、ハエが次の往復で羽根を戻す際に、航跡が羽根を押し上げ、揚力を生み出すことを発見した。
ディキンソン氏は昆虫の飛行物理学を解明するにつれ、ロボット開発に携わる人々の仲間入りを果たした。最近では、バークレー校の同僚であるフィアリング氏と共に、全長1インチ(約2.5cm)未満のクロバエのような装置「マイクロメカニカル・フライング・インセクト」の開発に携わった。この装置は海軍研究局と国防高等研究計画局の資金援助を受けて開発されている。しかしながら、このロボットクロバエは今のところ、テザー(紐)に繋がれた片方の羽根だけで飛行している。ディキンソン氏によると、最大の制約要因はバッテリーで、現状では大きすぎて電力不足のため、長時間飛行は不可能だという。
ディキンソン氏がロボット工学に興味を持つのは生物学者としての理由であり、次のオービル・ライトを目指しているわけではない。彼は飛行装置を、動物の仕組みに関する自身の考えを検証する機会と捉えている。「生物学では、何かを作って自分のアイデアを検証する機会は滅多にありません」と彼は言う。
ディキンソン氏は最近、研究室をパサデナのカリフォルニア工科大学に移し、学生たちと共に昆虫の飛行を研究するための装置の開発を続けています。例えば、ショウジョウバエ用の飛行シミュレーター「ロックンロール・フライ・アリーナ」などがその例です。このアリーナは直径6インチの中空の円筒形で、内壁には1万2000個の発光ダイオードが並んでいます。ディキンソン氏のチームは、アリーナ中央の鋼鉄製の棒の先端にハエを接着し、羽の動きを妨げないようにしています。ハエの周囲の壁は、棒や箱が変化するパターンで光り、ハエはアリーナ内を自由に飛んでいると錯覚します。
ハエが方向転換しようとすると、カメラが羽の動きの変化を検知し、その情報をコンピューターに送り、壁のライトを瞬時に切り替えます。ハエは障害物を避けるために、実際に方向転換していると「思い込み」ます。アリーナの名前の「ロックンロール」は、シミュレーター全体が縦横無尽に動かせることに由来しており、ディキンソン氏と学生たちは、ハエがジャイロスコープを使ってどのように方向転換するのかを研究することができます。
このアリーナは、ディキンソン教授のチームがハエの運動を規定すると考えられる一連の法則を解明するのに役立ちました。ハエが物体に向かって移動すると、その物体はハエの目の中で大きくなります。もし物体が片方の目でもう片方の目よりも大きくなれば、ハエはそれを避けるために方向転換します。もし物体が正面で大きくなれば、ハエは脚を伸ばして着地します。この理論を検証するため、ディキンソン教授と学生たちは「フライボール」(目玉のようなもの)と呼ばれる機械を製作しました。
フライボールは、トラックシステムに設置されたビデオカメラで構成されている。カメラは、白と黒の正方形がランダムに並べられたアリーナを周回し、撮影した映像をコンピューターに送信する。コンピューターはディキンソンのルールを用いて、次にどこへ進むかを選択する。ディキンソンは、コンピューターがハエのように方向転換することを期待している。「図を描くのは良いが、実際に何かを作るには、口先だけでなく行動で示さなければならない」。もし彼の考えが正しければ、カメラは本物のハエと同じ飛行経路を辿るだろう。そうでなければ、壁に衝突するかもしれない。
ディキンソン氏は最終的に、ハエの飛行についてこれまでに学んだ知識をすべて活用し、さらに大きな問い、すなわち昆虫の飛行がどのように進化したかという問いに応用したいと考えています。昆虫はおそらく3億年以上前に体の鱗から羽を発達させました。羽は昆虫の成功の秘訣であり、地球上で知られている動物種の大部分は飛翔昆虫です。飛翔の起源以来、昆虫はトンボの広い滑空翼からスズメバチの激しい戦闘機攻撃まで、様々な飛翔スタイルに対応するために解剖学的構造を微調整してきました。「行動がどのように進化するかを理解するには、まずそのメカニズムを理解する必要があります」とディキンソン氏は言います。
しかし、ディキンソンにとって、すべての疑問に答えが出る日が来るとは想像しにくい。「ハエの飛行を研究すればするほど、自分たちの理解がいかに乏しいかを痛感するのです」と彼は言う。
好例を挙げよう。学生たちの学習状況を確認するために部屋を回った後、ディキンソンはオフィスに戻ると、研究室のポスドク研究員マーク・フライが助けを求めてきた。フライは、空中を飛ぶショウジョウバエをシミュレートするコンピュータプログラムを書いていた。これはいわばフライボールの予行演習のようなものだ。シミュレートされたショウジョウバエは、チームが作成した決定ルールを用いて、シミュレートされたアリーナ内を移動する。しかし、うまくいかない。
「一方向にだけ回転させることができれば、うまくいきます」とフライ氏は言う。しかし、シミュレーションしたハエにどの方向に回転するかを選ばせると、結果は狂ってしまう。
ディキンソンはいくつか提案をする。昆虫に目の前のものだけでなく、少し前に見たものにも反応させるようにしたらどうか。フライはそれをどうプログラムに組み込めるか考え、しばらくして二人とも少し苛立ち、黙り込んでしまう。するとフライは、ディキンソンのチームのモットーとも言える3つの言葉を口にする。この言葉は研究室の黒板によく書かれている。
「小さな(罵り言葉)ロボット。」
ディキンソンは微笑みながら、同じ言葉を繰り返す。「ちっちゃな(汚い)ロボットたち」。神経学的に言えば、ほんの数個の回路しかない、一見単純な生き物であるこのハエは、それでも彼を毎回困惑させる。しかし、実際には、ディキンソンのモットーは愛情の言葉なのだ。「ハエは不思議な生き物です」と彼は言う。「おそらく地球上のすべての人間が1日に少なくとも1匹はハエを目にしているでしょう。なのに、私たちはそれに気づきもしません。私たちのすぐ目の前に、この驚異的な小さな機械が存在しているのです。」
カール・ジンマーの著書には『進化:あるアイデアの勝利』などがある。彼は現在、1600年代の神経学の起源に関する本を執筆中である。



