
民間生活を一変させた軍事発明のリストは長く、少なくともローマ帝国の道路網(軍隊の移動のために建設されたが、キリスト教の普及と世界初の郵便システムの基盤となった)まで遡ることができる。あるいはそれよりもさらに古いとも言える。近年では、こうした技術移転のプロセスによって、インターネット、GPS、そしてアナスタシア・マルクス・デ・サルセドが新著『戦闘準備キッチン:米軍があなたの食事のスタイルを形作る』で説明しているように、子供の弁当の中身ももたらされた。
戦場で軍隊に食料を供給することは、永遠の兵站上の課題であり、過去5千年にわたり、様々な独創的な解決策を生み出してきました。マルクス・デ・サルセドは、戦闘糧食の先史時代を巡る旅の中で、モンゴルのジャーキーとアステカの人食いについて語ります。前者は今でも軍隊の食事の特徴であり、後者は少なくとも、アメリカ軍の忌み嫌われているMREを少しは魅力的に見せてくれます。
産業革命期における食品保存技術における最初の大きなイノベーション、缶詰は、ナポレオン軍の食糧確保を目的としたフランス政府のコンペティションが一因となった。しかし、マルクス・デ・サルセドの記述が明らかにするように、ゴールドフィッシュ、グラノーラバー、ジュースパウチ、そしてスライスした全粒粉パンに挟んだ「自家製」ターキーハムサンドイッチを彼女の子供たちのお弁当に加えた戦争は、第二次世界大戦だった。「加工食品の世界において、第二次世界大戦はビッグバンだった」と彼女は記している。
世界中に散らばる何百万人もの兵士に食料を供給するという課題に直面した米陸軍は、マサチューセッツ州ネイティックにある陸軍自身の研究開発研究所で、あるいは大学と共同で、より軽量で長持ちするレーションの開発に、かなりの資金を投入した。軍は、有利な政府ベンダー契約に熱心であると同時に、一次研究に自社の資本を投入することを嫌うアメリカの食品企業に研究結果を共有した。この力学により、米陸軍の戦闘給食の目標は、驚くほど多くの食料品店の定番商品の根底にあることとなった。戦時中の血漿輸送における革新はインスタントコーヒーの道を開き、マック リブは「肉のモジュール加工」に関する軍の研究から生まれ、チートスの指を汚す粉は、1943年に政府の科学者が発明した乾燥圧縮された「ジャングル」チーズにまで遡ることができる。
マック リブは、「肉のモジュールを加工する」という軍事研究から生まれたものです。
しかし、国防総省からピグリー・ウィグリーに至るまでの道のりは、決して一直線ではない。パワーバーを例に挙げよう。マルクス・デ・サルセドによれば、その起源は第二次世界大戦中のローガンバー、あるいは緊急用Dレーションに遡る。これは栄養強化された食事代替チョコレートバーで、兵士たちが本当に必要な時に食べてしまう誘惑に負けないよう、意図的に溶けにくく、味も控えめに設計されていた。
戦後、溶けないチョコレートは別の研究プロジェクトに分離され(M&Msは別として、これはまだ未解決の問題です)、一方、ミール・イン・ア・バーのアイデアは、1969年に異なる条件下でのさまざまな食品の水分活性をマッピングする数学モデルが開発されたことで勢いを増しました。この研究はMITの科学者によって実施されましたが、資金提供はネイティック・センターが行いました。食品中に含まれる水分の量は、食品が腐る速さに大きく影響します。これを正確にモデル化できるため、科学者は食品の水分活性を下げるように配合を改良できるようになりました。その結果、「中間水分食品」という魅力的な名前のついた食品が爆発的に増えました。これには、柔らかくて噛み応えのある食感と、ほぼ永久に続く賞味期限という、これまで両立しない理想を兼ね備えたクッキー、バー、ペストリーなどが含まれます。
軍はピルズベリー社に最初のIMFバー(1970年に発売されたスペースフードスティック)の製造を委託しました。産業界がこの技術を採用し、その後、自社のリソースを投入して改良されたレシピと製造技術を開発するという明確な期待があったからです。10年も経たないうちに、ダイエット中の人やアウトドア愛好家が、強化エネルギーバー、ミールリプレイスメントバー、そして噛み応えのあるグラノーラバーをいち早く取り入れるようになりました。今日では、このカテゴリーはほとんどの食料品店で1つの通路を占有しており、アメリカ人の食生活の包括的なスナック化に貢献しています。一方、ネイティック基地の戦闘給食局の元局長は、マルクス・デ・サルセダ氏に、軍は現在、朝食、昼食、夕食という時代遅れの概念を「より軽食的なイベント」に置き換えることを検討していると語っています。
ここまではなかなか興味深いのですが、アナスタシア・マルクス・デ・サルセドの文体は、一部の人にとっては乗り越えられない難題となるかもしれません。確かに、バイキングの長船での生活を「ファイ・シグマ・カッパのビアポンナイトによく似ている」と表現したような描写や、「(警告:突飛な理論が続きます!)」といった括弧書きで本文を中断する彼女の癖は、面白がるというよりむしろイライラさせられました。
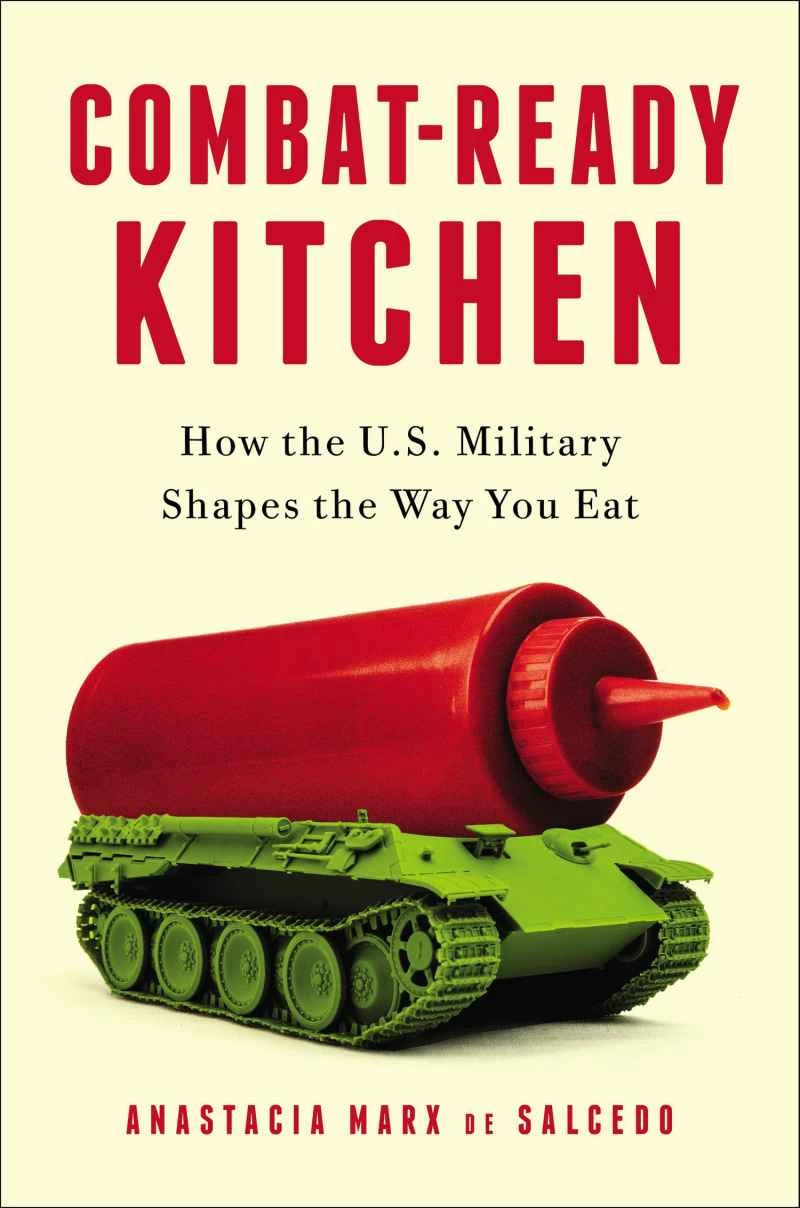
一方、彼女や多くの他のアメリカ人の親が子供に食べさせている特定の食品に焦点を当てることは、本の明確な物語構造に役立っているが、第二次世界大戦が世界の食料システムを再構築した他の同様に重要な方法のいくつかは必然的に省略されている。リジー・コリンガムは、最近の著書、 「戦争の味:第二次世界大戦と食糧をめぐる戦い」で、軍需品と戦車生産ラインを肥料とトラクターの製造に転換したことが、戦後の農業における緑の革命を加速させる上で重要な役割を果たした一方で、戦時中の食糧不足と代替品が、人々に豊かさを重んじ、品質の低い食材を受け入れるように仕向けたことを述べて、この点で貴重な背景を付け加えている。米国政府は、平時の需要の損害となる不況から農家を守ろうと不安を抱き、世界の飢餓を終わらせるという戦後のユートピア計画を妨害し、今日まで続く不平等を助長することさえあった。
しかし、アナスタシア・マルクス・デ・サルセド氏のより重要な指摘は的を射ている。軍のニーズは食品業界の研究計画の形成において過大な役割を果たしており、その結果、健康、味、環境持続可能性よりも、携帯性、利便性、保存期間、大衆受けを重視した製品が蔓延しているのだ。現代の多くの活動家は、アメリカの食料システムを変える責任を消費者に負わせている。結局のところ、グラノーラバーやジュースパウチを買うかどうかは、私たちにも選択権があるのだ。だからこそ、軍が食品研究への最大の投資者であるならば、その計画は必然的にアメリカの食生活を形作ることになるという明白な事実を指摘する人がいるのは、なおさら新鮮だ。
「もしネイティック・センターが存在しなかったら、私たちの食糧は一体どうなっていただろう?」と、マルクス・デ・サルセドは最終章で問いかける。「この問いに答えることはできない」と彼女は結論づける。しかし、もし税金で賄われている食品研究開発を軍事目的から切り離すことができたら、どうなるだろうかと考えてみたら、素晴らしいと思いませんか?
